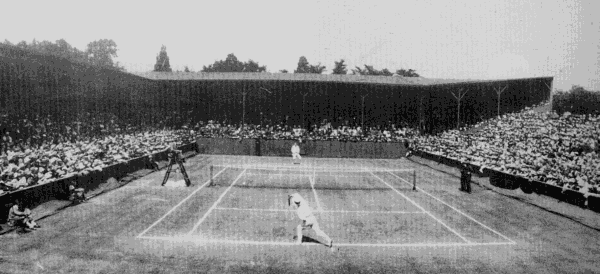走れメロス続いて、国語の教科書で読んだ話の記憶です。実はもう一つぐらいしか記憶に残ってなくて、これが「やわらかなボール」(教科書の題は違ったかもしれません)です。メロスと違い、現在では教科書には採用されていない気もしますが、記憶に頼って当時の教科書の内容をアラアラに書き起こしてみます。
-
テニスの世界最強を決めるデビス・カップの決勝で日本とアメリカが対戦しました。アメリカは大男のチルデン選手、日本は小柄な清水善造選手です。満員の観客は見ただけで大男のチルデン選手の楽勝だろうとささやきあいました。ところが試合が始まると清水選手は健闘し、後1点で勝つところまでになりました。最後の1点を争う長いラリーが続きましたが、その時にチルデン選手が突然足を滑らせて転倒してしまいます。誰もが清水選手の勝利を信じました。強いボールを打ち込めば、チルデン選手が打ち返すのは無理だからです。
ところがチルデン選手が足を滑らせて転んだのを見た清水選手は、なぜかやわらかなボールを打ち返します。これを何とか打ち返したチルデン選手は盛り返し、最後は逆転勝ちを収めます。敗れた清水選手ですが、相手の弱みに付けこまない立派な選手だと、勝ったチルデン選手以上の称賛を受けました。
 |
この「やわらかなボール」の検証は上前淳一郎氏が詳細にされています。検証の結果としては教科書のデ杯でのやわらかなボールは否定しています。では「やわらかなボール」はまったくの虚構かと言えばそうとも言い切れず、近いエピソードは間違いなくあります。どうも教科書に載せる時に適当にエピソードをつまみ食いしながら作り上げたんじゃないかとしています。事実としては日本はデ杯の決勝に進出していますし、そこで清水とチルデンが戦い、チルデンが勝ったのは事実だからです。
それでは「やわらかなボール」のエピソードは完全にでっち上げかと言えば、これまたそうではなさそうの検証もなされています。手元に上前氏の本がないので記憶に頼らざるを得ないのが苦しいところですが、清水の活躍の舞台は全英オープンです。当時の全英オープンはチャンピオンシップ制を取っており、オールカマーズと呼ばれる挑戦者予選を行っていたそうです。チャンピオンは予選から勝ち上がった挑戦者と対戦するぐらいの形式です。清水は全英オープンで大活躍し、1920年には決勝進出、1921年には準決勝進出を果たしています。これもまたビックリ仰天の記録です。
1920年の決勝の相手が実はチルデン。チルデンは当時のテニス王とも言える強豪で清水は4-6、4-6、11-13と敗れています。この時の対戦に「やわらかなボール」的なエピソードがあったかと言えば、wikipediaより、
「やわらかなボール」が放たれたのは、1919年ウィンブルドン選手権のオールカマーズ決勝(現在の準決勝)である。対戦相手のチルデンが足を滑らせて転倒、その時にゆっくりとしたボールを返したという。チルデンが態勢を立て直し、返球がエースに。「ヘイユー!ルック!!」とチルデンがラケットで指した所、観客がスタンディング・オベーションで清水に向かって拍手をしていた。結果としてチルデンが勝ち、二人が会場を後にしたものの、その後しばらく拍手が続いたという。
これについて上前氏は生前の清水の話を関係者から取材されていました。清水自身は「チャンス」と思ったそうです。ただその時にチルデンが倒れた右側に打ち返そうか、それとも左側に打ち返そうかの判断を一瞬迷ったそうです。迷いながら打ち返したら「打ち損ねて」チルデンが打ち返しやすい打球になってしまったとの事です。清水自身は温情をかけるつもりはなかったのに、結果としてそうなってしまったのは心外みたいなお話です。その場面で清水が本当は何を考えたのかは確認しようもありませんが、生前の清水はそう語っていたとしています。
もう一つ、やわらかなボールに関連する話が1921年の全英のオールカマーズ準決勝です。この時の対戦相手はスペインのマニュエル・アロンソ。この準決勝も清水は有利に試合を進めていたとなっていますが、ふと見るとスペイン国王が臨席されていたそうです。それを見た清水は「圧勝じゃ悪いかな?」の心がよぎったとされます。ところが試合の流れとは微妙なもので、清水がそう思った時から流れが変わり、結局この試合に敗れます。清水はどうやらこのエピソードを後年繰り返し話していたようです。もちろん慢心を戒める教訓としてです。
どうもなんですが、1920年の全英のオールカマーズ決勝、1921年の準決勝、もちろん1921年のデ杯決勝のエピソードを組み合わせて出来上がった話ではなかろうかとされています。根強くと言えば1921年のデ杯のチルデン戦もそうで、この時はチルデンも体調不良もあり清水が2セット先取したとなっています。3セット目も5-4としてのマッチポイントで線審が故意にレットの宣告を行い、清水のペースを狂わせてチルデンの逆転勝ちを招いた伝説です。これは伝説と言うより完全なフィクションであると上前氏は詳細に検証されていました。この誤審の話は、20年前ぐらいに作られたはずですから、それぐらいデ杯の清水-チルデン戦はアメリカでも伝説化されているのかもしれません。
清水のプレースタイルは今で言うならベーラインプレイヤーだったと上前氏の記述から想像しています。それも非常に卓越したもので、それこそ相手がどんな打球を打ち込んでも返してしまうとなっています。相手はまるで壁を相手にテニスをやっているような状態になり、根競べで自滅するみたいな感じでしょうか。また非常にクセのある打ち方をしていたようでwikipediaより、清水のショット、特にフォアハンドは、当時のテニスの評論家から観れば醜いものであった。通常、右利きであれば、左足が前に出るのであるが、テニスをしたての頃の清水は右足が前に出たという。このスタイルは、後期こそ無くなりつつあったものの、基本的な体の動きは終生変わらず、チルデンと対戦した時にも時折、右足が前に出たらしい。当然、この打法は今でも「基本でない」と言われているが、右足が前に出る事で、自然に上半身、上腕が足より遅れるように現れ、結果として現在の基本であるインサイドアウトの状態になったようである。事実、身長や手足の長さ等で、他の外国人選手に劣る清水が、強豪を上回る鋭い回転がかかったショットの持ち主であった。現在に通じる打法をこの黎明の時代にいち早くに身につけていたという驚愕の事実も忘れてはならないであろう。
テニスに詳しくないので何が書いてあるか半分以上判らないのですが、上前氏の記述では「こすり上げる様なショット」と言う表現がなされています。個人的には強いオーバードライブがかかる様なショットを勝手に想像しています。これまた上前氏の記述には清水の独特の打ち方は、バックハンドの弱点を克服するために、すべてのショットをバックハンド的に打った結果ではないかともなっていました。自分で書きながらサッパリわからないのですが、テニスに詳しい方がおられたら補足説明宜しくお願いします。残されている画像が少ないのですが清水とチルデンのショット時の画像を並べてみます。
 |
 |
-
スマイリー・シミーのファニー・テニス(奇妙なテニス)
 |
さてチルデンですが、全盛期の清水でも届かなかった強豪です。長身から繰り出される「キャノンボール」と称された強烈なサーブも有名ですが、他の技術も優れていたとなっています。4大大会10勝は歴代6位となっていますが、これも時代を考慮する必要があり、現在のようにワールド・ツアーで世界を転戦できる時代ではありませんでした(大陸間の移動は船ですからねぇ)。さらに言えば全仏は1924年までフランス人だけの大会でチルデンには出場資格すらなかった時代です。当然清水にも出場資格はなく、全英では活躍していても全仏に足跡がないのはそのためです。当時もアメリカのテニスは世界一でしたが、チルデンは全米で7度の優勝を飾っており歴代1位です。残りは清水にも勝った全英を3回制しています。まさにテニス史に残る強豪であり、当時はテニス王の名を欲しいままにしていたぐらいで良さそうです。
ただチルデンには光と影があります。光は上述した通りですが、影は栄光を極めた後に訪れます。当時のプレーヤーはアマチュアです。清水も本職は三井の社員です。スターであったチルデンはアマチュアであることに飽き足らずプロに転向します。つうてもプロ組織自体がなかったので、自分でチルデン・ツアーと言うプロ組織を作ってのものです。しかし運営はドンブリ勘定で次第に苦しくなったようで、晩年は安ホテルでアマチュア時代に獲得した銀杯を切り売りしながらの貧乏生活を余儀なくされます。さらにがあり、チルデンには少年愛の嗜好があり、これが問題視されて実刑まで受けています(大スキャンダルだったようです)。そのためにテニスでチルデンの事を語るのは長い間タブーになっていたとも伝えられます。
チルデンはデ杯戦の関係や後述する熊谷一弥との交流から日本にかなり好意を持っていたとされます。チルデン・ツアーは日本も訪れた事があり、佐藤俵太郎をチルデン・ツアーに誘ったり(日本のプロプレイヤー1号)もしています。清水とも交友関係があったようで、第二次大戦の荒波を潜り抜けた清水は、デ杯監督として1954年にチルデンの墓参りをしたとなっています。その時に清水は在りし日のチルデンを偲びながらこう漏らしたと伝えられています。
-
テニスでは君に勝てなかったが、人生では僕の方が幸せだったかしれないねぇ
デ杯は1人では戦えません。1921年の決勝進出の立役者は清水ともう1人、熊谷一弥の存在が巨大です。
 |
当時のアメリカテニス界は「リトル・ビル」ことビル・ジョンストンが君臨しているところに、「ビッグ・ビル」ことビル・チルデンが挑みかかる勢力構図です。熊谷はジョンストンには勝った事もあったようですが、清水同様にチルデンには勝てなかったようです。もっともチルデンは偉大なチャンピオンで、清水や熊谷が勝てなかったと言うよりも、誰もチルデンには勝てなかったとする方が正確かもしれません。アメリカで大活躍している熊谷と、イギリスで大活躍している清水を組み合わせてデ杯に参加したらと勧めたのは、誰だっけ、アメリカ人だったと思います。このアドバイスを聞いて日本で急遽デ杯参加のために庭球協会が作られたと上前氏は書かれていました。
デ杯は団体戦ですが、実のところ2人で団体が組めます。シングルス4試合、ダブルス1試合が基本ですから、2人でシングルスを2試合づつ行い、ダブルスをその2人で組めば団体チームの出来上がりです。実際は柏尾誠一郎を入れた3人でチームを組んでいますが、1921年のデ杯には柏尾は選手としては出場していません。柏尾も1920年のアントワープ五輪で熊谷とダブルスを組んで銀メダルを獲得した実力者ですが、1921年段階では清水、熊谷の二大巨頭の下でマネージャー役みたいな感じだったと伝えられています。
日本はデ杯のオールカマーズ決勝でオーストラリアに勝っていますが、全英で活躍していた清水と、アメリカで活躍していた2人の実力者が居たわけですから、勝っても不思議とは言えない気もします。ただ上前氏の調査によると1921年時点で清水は生涯のピーク的な時点としていますが、熊谷の方は1918年に全米の準決勝進出がピークであったと推測されており、その点は少し惜しんでおられました。ただ当時のアメリカの二人のビルは手ごわく、熊谷がたとえピーク時であってもアメリカに勝てたかとなると、やはり難しかったんじゃないかともされています。伝説のテニス王チルデンはそれぐらい強かったと言うところです。
もう一つ、1921年のデ杯の2人はシングルスのプレーヤーとしては世界最高峰に属していたとして良いと思いますが、ダブルスは少々苦手だったようです。準決勝のオーストラリア戦も負けています。上前氏の本の記憶に頼るので間違っている部分もあるかもしれませんが、デ杯戦時の熊谷は不調でした。たしか前半のシングルスでも負け、次のダブルスも不調です。熊谷はパートナーの清水に「もう負けよう」ともちかけます。体力の温存を図り最後のシングルスにすべてを賭ける作戦です。清水はやや不本意であったようですが「これも作戦」と同意します。熊谷は残された力をすべて注ぎ込んでシングルスに勝ちアメリカへの挑戦権を得る事に成功したとなっています。
しかしこれがアメリカ相手なら話が変わります。アメリカ戦でダブルスで負けると、ジョンストン相手に2勝した上で、熊谷か清水のどちらかがチルデンに勝つ必要があります。ジョンストンも強豪で全盛期の清水や熊谷なら「勝つ事もありえる」程度の相手です。実際は5戦全敗でしたが、あの時のデ杯で勝てる可能性はたとえ熊谷が絶好調でも難しかったぐらいのところでしょうか。それでも日本が世界の頂点にたった一度だけ近づいた瞬間であったのだけは間違いありません。
日本のテニスの黎明期に突然現れた清水、熊谷の二大巨頭でしたが、その後継者に位置付けられる名プレーヤーです。お手軽にwikipediaから戦績を拾っておけば、
| 年 | 成績 |
| 1931 | 全仏ベスト4 |
| 1932 | 全豪ベスト4.、混合準優勝、全英ベスト4 |
| 1933 | 全仏ベスト4、全英ベスト4、ダブルス準優勝 |
2013年現在も、四大大会での四強入5回と四大大会シングルス32勝はの日本テニス史上の最多記録であり、男女を問わず佐藤に並ぶ活躍を見せた選手は出ていない。
ちなみにデ杯でもシングルス14勝4敗、ダブルス8勝2敗の記録を残しています。伊達公子も記憶に残る名選手ですが、ベスト4は3回です。時代が違うと言えばそれまでですが、日本テニス史に残る偉大なプレーヤーであるのは間違いありません。後はオマケのオマケなんですが、清水、熊谷、佐藤は凄い成績を残してはいますが、残念ながら優勝には手が届いていません。日本人も4大大会で優勝記録はあり、
| 年 | 大会 | 種目 | 選手 |
| 1934 | 全英 | 混合複 | 三木龍善、ラウンド |
| 1955 | 全米 | 男子複 | 宮城淳、加茂公成 |
| 1975 | 全英 | 女子複 | 沢松和子、アン・キヨムラ |
| 1997 | 全仏 | 混合複 | 平木理化、ブバシ |
| 1999 | 全米 | 混合複 | 杉山愛、ブバシ |
| 2000 | 全米 | 女子複 | 杉山愛、アラール |
| 2003 | 全仏 | 女子複 | 杉山愛、クライシュテルス |
| 2003 | 全英 | 女子複 | 杉山愛、クライシュテルス |
一方でそこから22年後の平木・プバシ組の全仏制覇は今回調べるまで存じませんでした。扱いはスポーツ面に留まり沢松・キヨムラ組の時のように社会面扱いにならなかったぐらいでしょうか。杉山愛も活躍していたのは知っていましたが、4回も優勝しているのは正直ビックリです。この辺は日本のテニスのレベルが上がり、ダブルス優勝ぐらいでは騒ぐほどの事はないとなったのでしょうか、それとも時代のトレンドの変化でダブルス優勝の価値が下がったのでしょうか、はたまたテニスの地位が低迷してしまったのでしょうか。
でもって今は錦織圭の時代です。新たな伝説を残してくれる事に期待します。